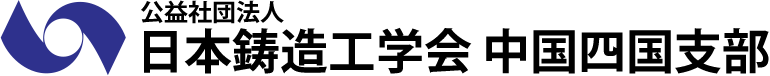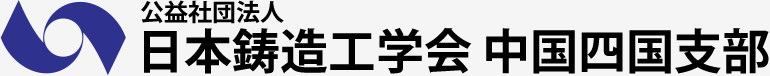工学とは、サイエンスの技術を社会に役立てるもの。
そして簿記とは、お金を扱う(工学的)技術です。お金という数を扱う経理ソフトは、表計算のデータベースそのもの。
工学が社会活動なので、お金の知識は必須です。お金を扱う技術は簿記(Bookkeeping)とか会計(Accounting)。
詳しい実務は、会計係に任せても工学者は基本的な考え方・扱い方と、表現方法を理解できることが必要です。
日本の工学教育では、お金の扱い方を教えていません。お金がわからないために工学者は会社の中でバカ扱いされたりして損してる。
知らないことを学ぶには、動画が一番。
その前に、お金を考察してみよう。
犬・猫・サルにお金を見せても反応なし。
しかし、人はお金を見ると「これでものが買える」と。人だけが持つ効用の交換価値を抽象的概念として認知するのが「お金」。
お金は、数字で表現される。
古代、お金は 貴重な貝殻やお米などがその機能、次に貨幣、その次がお札(紙に印刷)、現代は電子マネーに。
イタリアで発明されたのが「複式簿記」というお金を扱う技術で、今に至るまで基本は同じ。
複式簿記では、 お金で表現できる 資産・負債・自分のお金(純資本)、 何かをする費用と収入、 という大きな分類を行い
お金の移動や価値の交換を、
左側(資産が増える側)=右側(その源泉・原因)
という等式で表現。
一方、子供のころからのお金の扱い方は、収入と支出と残高だけなので単式簿記という。現金出納帳がこれ。
単式簿記と複式簿記の違い
単式簿記では、もらった現金から、支出が出て行って、残高が記載される。
・現金を預金しても支出になり残高が減る。ちょっと変。
・現金で金塊を買っても支出だから残高が減る。これも変だぞ。
・後で支払う約束で物を買ったので今は現金支出しない、残高同じ、これも変だ。
複式簿記では、 現金を預金すると 預金増加=現金の減少
現金で金を買うと 金資産増加=現金の減少
掛けでもの買うと もの増加=負債増加
掛けを支払うと 負債減少=現金減少
となって、
現金は減っても、他の資産に変わっているだけで資産は増減なしと解る。
掛けで買うと、負債が増えて、現物資産が増える。支出でものが手に入る等価取引と解る。
企業活動は、複式簿記でないと理解と記録ができない。
新しい概念は、動画で勉強が早い
実は、簿記の勉強するには、手っ取り早くなら経理ソフトを買って入力してみるのが一番だ。
工業簿記は難しい。概念学ぶならば、商業簿記の入門編の安価な経理ソフトに「データ入力したらすぐわかるようになる」。
筆者は、「わくわく財務会計(https://www.lan2.jp/acc/as.html)」を推奨。
以前は、大番頭という有名な中小企業向け会計ソフトを運営していた人たちが、買収されて別会社を作り作成したソフトなので機能はしっかりしてる。家計簿にしてもよいし、テスト的に1ヶ月無料版で勉強してもよい。
特筆すべきは、追加料金が不要なこと。多くのソフトがメンテナンス有料ですが、基本部分に変更がなければ、個人使用ならバージョンアップはほぼ不要です。
データを入れて使ってみたら、その意味がすぐ分かるようになり、きっと継続使用したくなります。
経理ソフト使えば、個人事業始めたら青色申告が使え65万円の所得控除も使えます。家計簿にもなります。家の資産管理にも使えます。個人でも団体でも家族それぞれも別々に管理が一つのアプリで使えるようになります。ネットのアプリでは、一つ一つにそれぞれお金がかかります。大きな違いですね。
そして、経理ソフトにデータ入れると自動で作成される財務諸表で、個々のお金の出入りが財務諸表にどのように反映されるかがわかるので、会社や団体の財務データもすぐに理解できるようになります。
参考になるもの
例: 下記の動画など (ネットで分かりやすそうなもの多数あり、調べて自分にあったものを)