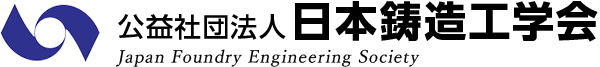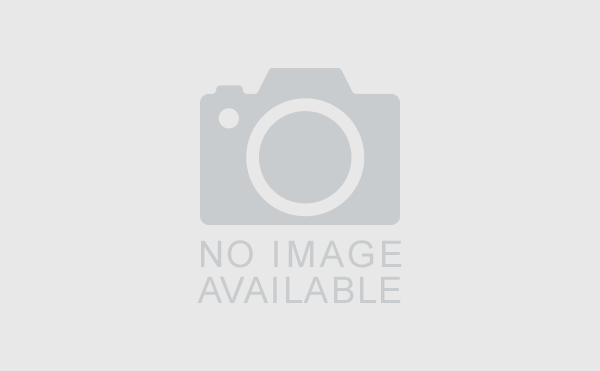第4回:オンライン講座「理事による技術・情報・文化発信講座」(会員聴講無料)のご案内
オンライン講座「理事による技術・情報・文化発信講座」 第4回のご案内
公益社団法人日本鋳造工学会では,理事(有志)による無料で聴講できるWEB講座を開設しました.会員の皆様には無料でご聴講いただけます.日本鋳造工学会の会員,若手・中堅の方,技術・業務面においてヒントを探しておられる方,いまさら聞けない話など,鋳造に関わる専門家が解説するこの機会をぜひご利用いただき,鋳造工学への理解を深めていただきたく,ご案内申し上げます.
第4回は3名の講師により,CAE の活用方法,鋳造過程の可視化,鋳物の変形や残留応力に関する講演を予定しております.どうぞふるってご聴講ください.
オンライン講座スケジュール
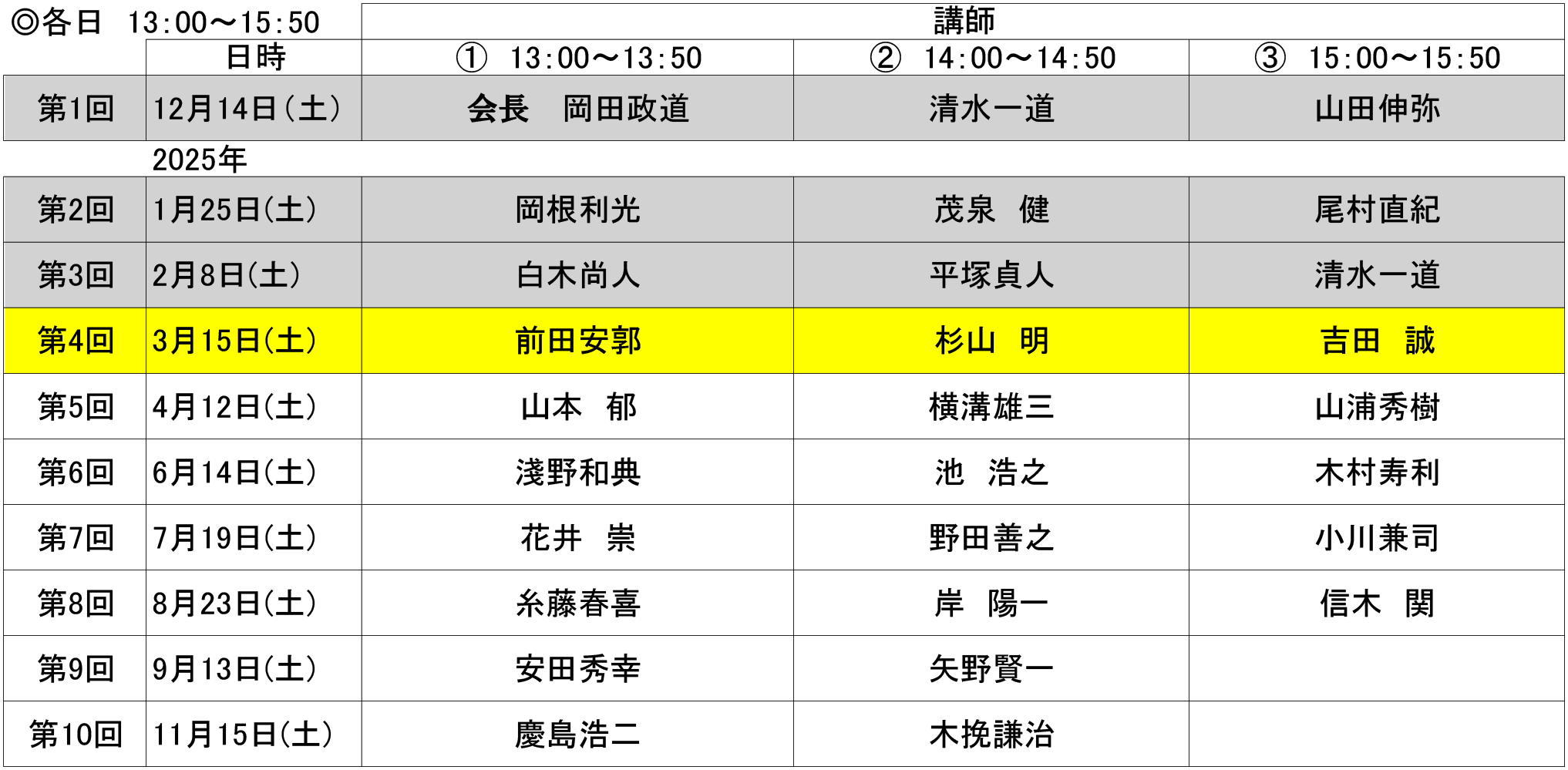
*本講座はZoomを使用したオンライン講座です.必要なアプリケーションのインストール,通信環境は参加者ご自身で用意ください.
*日本鋳造工学会会員(正会員・維持会員・学生会員・外国会員)を受講対象としています.ただし,維持会員は代表者他1~4口は5名まで,5口以上は10名までご参加いただけます.
*現在会員でない方はご入会いただくことで聴講が可能です.本講座聴講希望の方は入会金が無料となりますので,積極的なご入会をお待ちしております.
参加方法
【日本鋳造工学会会員の方(正会員・維持会員・学生会員・外国会員)】
・2月14日配信のメールマガジンに記載されているURLからサイトにアクセスし,申込フォームに必要事項入力の上送信ください.折り返し参加方法を記したメールが届きます.
・メールマガジンが届かない,あるいはメールアドレス未登録の方は下記フォームからお申込みください.折り返しご案内を送信します(次回もメールマガジンでご案内を配信しますので,メールアドレスをご登録(更新)いただくことをお勧めします).
↓こちらからご登録ください↓
![]()
【会員以外の方】
・下記より,日本鋳造工学会へのご入会手続きをお願いいたします.
・本講座参加者の方は入会金が無料になります.この機にぜひご入会ください.
入会申込フォーム最下部の備考欄に「理事によるオンライン講座」とご記入ください.
↓入会はこちらから↓
![]()
【 第4回 】3月15日(土) 13:00~15:50
1)13:00~13:50 講師:前田安郭(大同大学)
テーマ:鋳造CAEの湯流れ,伝熱,凝固解析の技術動向
鋳造CAEシミュレーションを使っていて,実測(実験)結果と合わないと感じていませんか.鋳造CAEの「どこの設定」が悪いのでしょうか.鋳造CAEのV&V (Verification and Validation)を考える上で,特に湯流れ解析,伝熱・凝固解析で是非理解しておいてほしい解析技術や設定方法,チェック項目があります.例えば,形状近似の問題,界面捕捉法とは,温度と固相率の関係などです.ここでは,いくつかの解析技術をできるだけ簡便に概説したいと思います.鋳造CAEは使い方を誤らなければ非常に有用で強力なツールです.正しく活用していきましょう.
<10分間休憩>
2)14:00~14:50 講師:杉山 明(大阪産業大学)
テーマ:鋳造過程の可視化事例の紹介
鋳造において,注湯過程や凝固過程で生じている現象を正確に把握することは,健全な鋳物の製造において重要です.しかしながら,通常は鋳型が不可視であるため,温度などの間接的な情報,あるいはCAEなどを活用した現象の予測が多いと思います.そこで,今回は透過X線を利用して直接的に観察した,様々な事例を紹介したいと思います.可視化のために形状の制約があるため,単純形状の事例となりますが,生じている現象は複雑な鋳物にも通じる部分が多くあります.これらの事例が鋳造現象の理解への一助となれば幸いです.
<10分間休憩>
3)15:00~15:50 講師:吉田 誠(早稲田大学)
テーマ:鋳物の変形と残留応力予測の研究動向
鋳物の冷却時に発生する反り変形や残留応力を製品設計や方案検討時に予測するニーズがある.焼きなましや後加工による対策もあるが生産性に難がある.これらの予測はCAEロードマップ上鋳巣予測よりも先の課題に位置づけられている.流動凝固解析に引き続き,鋳型と鋳物の双方を含めた熱応力解析を実施する必要があり,難易度がさらに上がるためである.しかし世界的にはドイツ・米国を中心に研究段階から実生産適用段階に入りつつある.本論では鋳物の変形や残留応力の発生過程について実験例を中心に紹介し計算例についても紹介する.