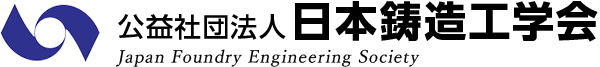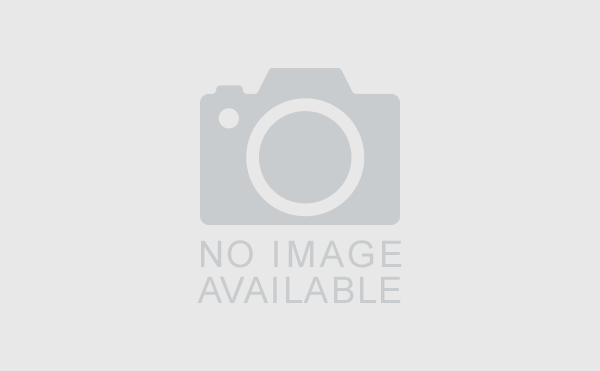ダクタイル鋳鉄を現状インサ-トで黒皮から加工しているのですが,黒皮のみを一回加工で取り除いてからインサ-トで加工したほうがインサ-トの寿命としてはよくなると思いますか?
加工品質の安定化,低コスト化という視点から素形材側の影響を知りたいということから,鋳鉄素材を加工する際に黒皮を取り除く必要性があるかどうかという質問を多くの方から受けることがあります.本来であれば,被削材(鋳鉄素形材)の調査,データ解析に基づき,加工方法に関する意見交換を行うことがベストですが,まずは一般的な要因を紹介します.
加工に影響を与える被削材(素形材)の主な要因は大きく2つです.一つ目,鋳鉄素材の<基地組織>です.一般的な鋳鉄素材の基地組織はフェライト系組織で構成される素材(FCD400やFCD450など)とパーライト系組織で構成される素材(FCD600,FCD700,FC250,FC300)に分類されることはご存じだと思います.ところが,最表層部分(約1mm以内)は素材冷却時に空気中の酸素と触れることで黒鉛が欠乏状態となり,黒鉛がほどんど存在しないフェライト基地組織(脱炭層)に変化しています.フェライトは粘りが強いという特性があり,加工刃具の表面に付着しやすくなります.素材内部組織と素材表層部組織の違いを調べ,それに適した加工方法を選択することで,加工品質,加工刃具の寿命延長などの可能性が高くなると思います.
二つ目,鋳鉄素材の<表面異物の有無>です.鋳鉄は約1400℃の溶湯を鋳型に注いで,製造されます.そのため,耐熱性の高い鋳型が必要になります.そのため鋳型には珪砂などの砂を用いるのが一般的です.溶湯は鋳型に接触するとその隙間に差し込もうとする性質を持っていますが,砂の表面にコーティングされている粘結剤が溶湯の差し込みを防いでいます.その働きが弱い部分は砂一粒(約0.3mm)程度,溶湯の差し込みが発生,鋳鉄素材最表面(約0.5mm以内)は異物(砂)を巻き込んだ状態になっています.この異物が加工刃具の異常を招くので,まずはその除去を行う必要があります.
このことから鋳鉄素材最表面(黒皮部)をまず荒加工して,インサートなどの仕上げ加工を行うほうが良いと言われいる所以です.但し,荒化工→仕上げ加工という工程設計はコスト上昇を招く可能性があるため,素材表面の異物観察を入念に行い,加工手順の検討を行うことをお勧めします.
(『鋳造工学』97巻2号掲載)