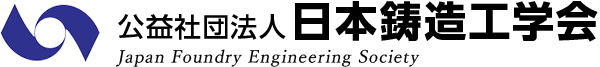鉄
鋳鉄にめっき処理は可能なのでしょうか? 実際に適用されている例(部材とめっきの種 類)があれば教えて下さい.
鋳鉄にめっき処理は可能です.ただし,鋳鉄の鋳肌は一般的に凹凸が大きく,鋳物砂などの異物が多く,また,加工面においても黒鉛が晶出しており,これらがめっき後の仕上がりに影響を与えるため,適切な前処理が必要です. 実際の適用例 […]
片状黒鉛鋳鉄におけるK-FGIや肥痩度(DDT)とはどういう意味ですか.これらがどのような特性に影響するのでしょうか.
画素数150万画素数以上のCCDカメラを用いて,倍率×200の黒鉛組織画像を表示し,黒鉛組織画像の1mm×1mm枠内の平均径5μm以上かつ黒鉛面積率が54%以下の黒鉛の数をK-FGIとして定義されています.これは片状黒鉛 […]
鋳造工学第97巻(2025)第2号108 『江戸時代の鋳鉄製大砲』 の内容についてですが,図2の大砲の写真を見ますと型分割面がはっきりと写っており,図8に描かれている型方案で鋳造されたことがよく分かります.ところが,図1の大砲の写真には型分割面が無いように見えます.図8とは別の方案で鋳造されたのでしょうか.
確かに上の図1の大砲には型分割面は見えませんね(図1).しかし,この様な形の大砲を分割せずに鋳造できるのはフルモールド法 […]
FCでもFCDでも構いませんが,振動減衰性は組織(フェライト,パーライ ト)の影響を受けるのでしょうか.影響があれば,その理由も教えて下さい
FC,FCDの振動減衰性(振動エネルギーを吸収する能力のことで減衰能ともいう)は組織(黒鉛,基地)の影響を受けることが一般的に知られている1).基地組織では鋳放しFC材のパーライトが焼きなましフェライト化することで減衰性 […]
鋳鋼材は廃棄されると最終的にリサイクルされると思いますが,リサイクルするには専門的な特殊工程があるのでしょうか? 自社内または鋳造業者に廃棄材を持ち込んで再溶融し,別部品としてリサイクルできればコストメリットがあると見込んでいます.特殊な工程が不要であれば検討してみたいと考えておりますが,このようなリサイクルを行う場合に注意すべき点があればご教示ください.
リサイクルとして良い提案と思います.再溶融では,溶解,精錬,成分調整という標準工程が一般的です.リサイクルの場合の注意すべき点は再溶解に際して精錬で除去できない有害成分(Cu,Sn,Sb,Pb,As等) の混入を防ぐこと […]
FC材にTiを添加してフッシャー欠陥対策をすることがあるのですが,同時に硬度が低下することが多々あります.このメカニズムとして私の中では,Nがセメンタイトを安定化しているが,Ti添加によりTiNを形成し(エリンガム図的に窒化物を形成するのが安定な為),Nによるセメンタイト形成が抑制されるためと理解しています (TiNは軟らかいという認識) .この理解が正しいのか(今わかっている中で最も確からしいか)お伺いしたいです.
片状黒鉛鋳鉄へのチタン添加で生成する化合物は窒素量とチタン量で変化することが知られています.TiとNの原子パーセント比(Ti/N)が1以下であれば,TiN,1~4ではTiNとTiC,4以上であればTiCが生成するという報 […]
最新のJISで規定された固溶強化フェライト基地球状黒鉛鋳鉄の特徴と使用用途を教えてください.
ご質問には,「最新のJISで規定された」とありますので,従来からあるSi-Mo-FCDのような耐熱用途のものは除いて回答します. 固溶強化フェライト基地球状黒鉛鋳鉄(SSSGI : solid-solution stre […]
ダクタイル鋳鉄を現状インサ-トで黒皮から加工しているのですが,黒皮のみを一回加工で取り除いてからインサ-トで加工したほうがインサ-トの寿命としてはよくなると思いますか?
加工品質の安定化,低コスト化という視点から素形材側の影響を知りたいということから,鋳鉄素材を加工する際に黒皮を取り除く必要性があるかどうかという質問を多くの方から受けることがあります.本来であれば,被削材(鋳鉄素形材)の […]
鋳鋼では補修溶接を行うことがありますが,鋳鉄では補修溶接ができないと聞きました.なぜでしょうか? (質問者:TAKE TAKE)
鋳鋼と鋳鉄では,規定される炭素量が異なり,これに伴う組織形態の違いが補修溶接の難易度に大きく影響します.鋳鋼は一般的な鋼と同様にフェライト,パーライト,マルテンサイト等を有する組織形態のため,鋼に適用されている方法での補 […]
本誌70巻709頁(1998年10月),71巻104頁(1999年2月)などの論文で,球状黒鉛鋳鉄の表面と内部の凝固時間比で溶湯ひけ傾向が評価できるとありますが,なぜかわかりません.詳しく説明してください.
文意が読み取りにくい論文ですが,本文中で鋳物のひけ発生を表面と内部の凝固時間比から推測することは他の研究者も述べており,MDE値やマッシイ度として測定できる,としています. 中も外も同時に凝固する場合(凝固時間比1に […]