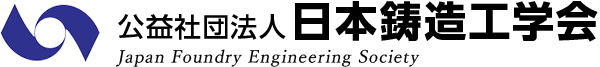Fe-C系状態図で黒鉛の晶出量を求めると数%ですが,顕微鏡組織から判定すると10~15%に見え,文献にもそう書かれています.この違いはなんですか?
Fe-C系状態図における黒鉛晶出量は,重量%で表示されています.一方,顕微鏡組織における黒鉛晶出量は体積%もしくは面積%で表示されています.よって,状態図の重量と顕微鏡組織での黒鉛体積%の間には,近似式で計算すると,式( […]
鋳鉄材料の規格は引張強さや伸びで規定されていますが, 値を求めるときの有効数字はどこまでですか? 具体的に教えてください.
引張試験は特殊な場合(規程の試験片が採取できないなど)を除いて,基本的にはJIS Z 2241「金属材料引張試験方法」に則った方法で実施する必要があります.一般に引張試験結果は, 材料規格に規定のない場合は, 少なくとも […]
私の職場では無機中子を使用し低圧鋳造アルミ合金鋳物を製作していますが,原因不明の中子折れが多発しています.今一番怪しいのは中子のなりより性だと思うのですが,なりより性の測定方式などは何があるのでしょうか?
なりより性とは,鋳型に溶湯が注入されて,凝固すると同時に収縮しますが鋳型が鋳物の収縮に応じて,ともに収縮に応じてくれる性質をいう用語で可縮性とも言います.これは非常に重要なことで,もしこの性質がないと鋳造品は肉の薄い部 […]
海外の高級車では,アルミボディ部品が使われているとよく聞きます.どんな工法でどんな材料が使われていますか?
オールアルミニウム合金のボディ構造を持つ乗用車を世界で初めて量産したのは,ドイツのアウディ社で,1994年に発売されたAudi A8です.このボディ構造は,アルミニウム合金の板材や押出材の部品をアルミニウム合金鋳物やダイ […]
接種は本当に黒鉛化を促進するのでしょうか?
Fe-G系凝固(共晶Fe3C:チルが無い)した鋳鉄の黒鉛量は,おおよそ凝固時の晶出量(Fe-C二元複平衡状態図のE´点)とその後の共析変態完了時までの析出量の和になります.接種は,基地組織(フェライト/パーライト率)にも […]
近年は生砂のCB値管理が主流になっていますが,同CB値でも水分が変わり不良への影響も変わることがあります.CB値,水分管理についてどう考えればよいでしょうか?
CB値(コンパクタビリティ)は,1970年にAFS掲載論文の中で提唱された生砂評価指標です.既存のサンドランマを使用して測定するという簡便性により日本でも広く採用されてきた経緯があります. 生砂評価指標としてのCB値への […]
鋳造」と言う言葉を使った人,または 「Casting」を「鋳造」と決めた人を教えて下さい.
鋳造は人類の歴史の中で最も古い時代に人々が身に着けた金属の熱間加工技術であり,既に約6000年の歴史を持っています.中国では紀元前1700~1000年に青銅鋳物の製造の最盛期を迎え,高度な鋳造プロセスを確立しています.中 […]
青銅よりも黄銅の方が湯が回りやすいのはなぜですか?
黄銅系の合金は凝固温度範囲が狭く,表皮形成型の凝固形態となり,青銅系の合金は凝固温度範囲が広く,粥状の凝固形態となることが知られています.表皮形成型の凝固形態となる合金では,流動中に鋳壁から凝固層が成長し,流路を閉塞する […]
マグネシウム合金は自動車の軽量化では優れていますが,精錬で大量のCO2を排出するそうです.どんな精錬方法でどれだけCO2を排出しますか?
現在マグネシウム精錬方法としては2種類の方法が主流で,熱還元法と電解法があります. 熱還元法の原材料は主にドロマイト(MgCO3*CaCO3)Mg含有量13%が使われています. 電解法では前記ドロマイトの他にカーナライト […]
よくアルミの値段はと聞くとLMEがうんぬんと話されることがありますが,LMEとはなんですか?
LMEというのは,London Metal Exchangeの略で,日本語ではロンドン金属取引所といいます.LMEはイギリスのロンドンにある世界最大規模の非鉄金属専門の取引所です.1877年に金属取引専用の施設を保有する […]