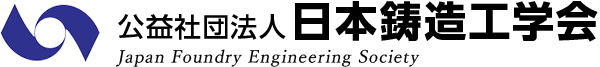鉛フリー銅合金が開発されていますが,銅合金中の鉛の役割は何だったのですか. また,それを他の元素で置き換えられるのでしょうか.
銅合金鋳物において,鉛と銅はお互いに固溶せず,凝固の結果,結晶粒界の最終凝固部に分散して存在します.柔軟性,潤滑性のある鉛が粒界に存在することにより,切削抵抗を下げる効果があります.青銅鋳物はバルブ等に用いられていますが […]
生型砂は融点が1710℃と高いシリカ(石英)で構成されているのに,なぜ焼付き不良が起こるのですか?
焼付きは物理的焼付きと化学的焼付きがあります.ご質問の焼付きは,ご質問内に「耐火度の高い石英」と受け取れます文言がありますので,ご質問の焼付きは,生型砂の耐火度低下により,金属酸化物と反応して生じる化学的焼付きと考えまし […]
FCでもFCDでも構いませんが,振動減衰性は組織(フェライト,パーライ ト)の影響を受けるのでしょうか.影響があれば,その理由も教えて下さい
FC,FCDの振動減衰性(振動エネルギーを吸収する能力のことで減衰能ともいう)は組織(黒鉛,基地)の影響を受けることが一般的に知られている1).基地組織では鋳放しFC材のパーライトが焼きなましフェライト化することで減衰性 […]
グリーンアルミとは何ですか? またグリーンアルミのCO2排出量が再生地金よりも多い理由を知りたいです.
グリーンアルミは,業界での定義はなされていないものの,一般的には,CO2排出量の原単位が約4kg-CO2/kg-Al以下のアルミ新地金と認知されています.グリーンアルミは,電解製錬時に再生可能エネルギーのような低CO2電 […]
鋳鋼材は廃棄されると最終的にリサイクルされると思いますが,リサイクルするには専門的な特殊工程があるのでしょうか? 自社内または鋳造業者に廃棄材を持ち込んで再溶融し,別部品としてリサイクルできればコストメリットがあると見込んでいます.特殊な工程が不要であれば検討してみたいと考えておりますが,このようなリサイクルを行う場合に注意すべき点があればご教示ください.
リサイクルとして良い提案と思います.再溶融では,溶解,精錬,成分調整という標準工程が一般的です.リサイクルの場合の注意すべき点は再溶解に際して精錬で除去できない有害成分(Cu,Sn,Sb,Pb,As等) の混入を防ぐこと […]
FC材にTiを添加してフッシャー欠陥対策をすることがあるのですが,同時に硬度が低下することが多々あります.このメカニズムとして私の中では,Nがセメンタイトを安定化しているが,Ti添加によりTiNを形成し(エリンガム図的に窒化物を形成するのが安定な為),Nによるセメンタイト形成が抑制されるためと理解しています (TiNは軟らかいという認識) .この理解が正しいのか(今わかっている中で最も確からしいか)お伺いしたいです.
片状黒鉛鋳鉄へのチタン添加で生成する化合物は窒素量とチタン量で変化することが知られています.TiとNの原子パーセント比(Ti/N)が1以下であれば,TiN,1~4ではTiNとTiC,4以上であればTiCが生成するという報 […]
最新のJISで規定された固溶強化フェライト基地球状黒鉛鋳鉄の特徴と使用用途を教えてください.
ご質問には,「最新のJISで規定された」とありますので,従来からあるSi-Mo-FCDのような耐熱用途のものは除いて回答します. 固溶強化フェライト基地球状黒鉛鋳鉄(SSSGI : solid-solution stre […]
ダクタイル鋳鉄を現状インサ-トで黒皮から加工しているのですが,黒皮のみを一回加工で取り除いてからインサ-トで加工したほうがインサ-トの寿命としてはよくなると思いますか?
加工品質の安定化,低コスト化という視点から素形材側の影響を知りたいということから,鋳鉄素材を加工する際に黒皮を取り除く必要性があるかどうかという質問を多くの方から受けることがあります.本来であれば,被削材(鋳鉄素形材)の […]
鋳造割れと引け割れの違いを教えてください
鋳造割れと称する場合,(1)凝固が始まって凝固が完了するまでに発生する割れと,(2)凝固が完了した後,鋳物が室温に達するまでに発生する割れの両方を含みます.この2つが区別されないことに注意が必要です.なぜかというと,防止 […]
シェル中子の臭気を減らすにはどの様な方法がありますか?
シェル中子の原料はフェノール樹脂をベースとしたレジンコーテッドサンド(RCS)ですが,中子成型時に加熱焼成することからガスが発生します.発生する主要なガスは,フェノール,アンモニア,ホルムアルデヒドなどで,これらが臭気の […]