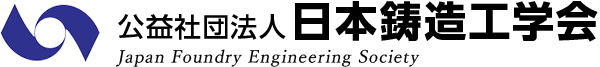鋳鉄溶湯の熱分析で得られる冷却微分曲線で,凝固終了時の傾きがマイナスからプラスに転じる点の角度θが小さいほど引けにくい溶湯だという文献がありますが,この理屈が良く分かりません.どういった理由で角度θが小さいと引けにくい溶湯だと言えるのでしょうか?
θが小さいことは熱電対を挿入した部位の熱伝導率が小さいことを意味しており,熱伝導率が小さくなる原因は,ひけ巣(空洞)の存在と考えられています.なぜ冷却速度曲線(冷却微分曲線)にθが表れるのかという点からもう少し詳しく説明 […]
「圧力容器(FC300)穴加工後の水圧検査で鋳肌面に微小な漏れが発生しました.原因としまして,どのようなことなどが考えられるでしょうか.また、黒鉛や粒界を介して圧漏れすることはあるのでしょうか.
漏れるということは内側と外側がつながった不良ということなので,考えられるのは割れや湯境、表面から見えにくい異物かみ(砂、ノロ)等の不良が考えられます.これらの不良は目視でよく見れば分かると思いますが,微小なものはわかりに […]
ダイカスト工場でIoTを進めなさいと上司に言われているのですが,何をすれば良いかわかりません.まずは,鋳造の計測だと思うのですが,鋳造機に使えるセンサーは何があるのでしょうか? また参考になる論文などあるのでしょうか?
質問者様の目的が不明ですし,また現在の鋳造計測状況が不明ですので,どこから進めればいいのか説明するのは簡単ではないのですが,一般にIOTのために新たにセンサーを設置して計測を始めても期待する効果が得られず失敗に終わるでし […]
鋳物砂の再生に寿命はありますか? 不純物(生型であればオーリティック,自硬性であれば樹脂)が再生されていれば新砂と同等と考えてよいですか?
「再生の寿命」の質問:鋳物砂(天然けい砂や人工砂など)に粘結剤などを加えて,造型可能な生型砂や自硬性鋳型砂とし,これらの鋳造後の回収砂を再生します.再生工程では,回収砂に対しての歩留りがあり,これが寿命に相当すると言えま […]
ダイカストについて初心者なのですが,ダイカストのオーバーフローについて,役割は理解したのですが仕組みがよく分かりません.なぜ金型に空間を設けることで,ガスや酸化物,介在物を排出できるようになるのでしょうか.そのメカニズムを教えて頂きたいです.
オーバフローの役割にガスや酸化物,介在物を排出すると教科書等に記載されていますが,実際のところは,①ガス抜きや溶湯合流部にオーバフローを設置してガスのトラップによる湯じわを無くすこと,②金型温度が冷えることで起きる離型 […]
生型砂の‘ねかせ’時間は2時間ほどといわれていますが,2時間で何が起こっているのでしょうか?
生型砂の粘結材であるベントナイトは,水を吸収し膨潤することで粘結力を発揮します.ベントナイトを水に投入し自然に膨潤するには数時間という時間を要するため,物理的に力を加える混練(ねり作用)が行われて使用されます.混練は3~ […]
マグネシウム合金の溶解作業で注意すべき点はなんでしょうか? カバーガスなどは何を利用すればよいのでしょうか?
まずはいつでも消火できる準備をすることが第一だと思います.溶解量にあった砂やフラックスなどの消火剤を準備してください.坩堝と炉蓋には隙間がないようにし,カバーガスによって炉内が常に正圧である事を確認してください.溶湯表面 […]
ねずみ鋳鉄FC200(JISG5501)で,別鋳込み供試材の規格がφ30に制定されているのは機械試験に使用するためでしょうか? 8B試験片にてφ20で鋳造し,φ12.5で引張試験を行うのは間違っていますか?
鋳鉄の引張強さは黒鉛量,炭素飽和度(Sc),肉厚などによって変化します.試験片の直径が小さい場合は,その鋳物の冷却速度が大きなり,引張強さは増大します.そこでJISなどでは,片状黒鉛鋳鉄の標準強さは直径30mmの試験の値 […]
K値の算出方法について,文献等には「K値=全介在物数/観察試片数」「2破面をもつ試片を1片と数える」と載っています.では,短冊状平板を5~6片に割った両端の試片は、片側1破面しかないので評価対象外となるのでしょうか? 片側のみの破面でも使用しても良いのでしょうか?
Kモールド法における試料採取では、短冊状試料を2本以上採取し、各試料から両側に破面を持つ観察用試片を5片以上採取し、合計10片以上としてK値を計算します. ただし、片側のみの破面でも使用して結構です.湯口部、先端部等を使 […]
鉄材の湯流れ性がCE値の違いで変化することを現場で経験しました.なぜでしょうか? また,湯流れ性は一般にどのように測定して判断するのでしょうか.
湯流れ性(流動性)は,鋳込温度が高くなれば凝固時間(流動寿命)が長くなり,その間に流れる距離も長くなります.過熱温度(=鋳込温度-液相温度)と流動性との間にほぼ直線関係が成り立つことが,実験的に確かめられています.鋳鉄の […]