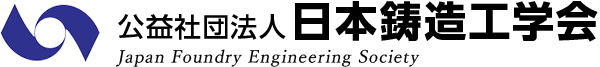鉄
研究室レベルでの実験において,鉄系材料を合金化する際に,どのような工夫がありますか? 溶けにくい高融点金属を効率よく溶かす工夫等を知りたいです. なお,黒鉛のように浮上しやすいものは,半紙やアルミホイールに包んで,鋳型底部にセットして溶かすと聞いたことがあります.
鉄系材料を合金化するために添加する元素はFeと比較して融点が高いものが多く,純金属のまま溶湯内に添加すると,酸化性の強い金属は表面に生成する酸化物相により溶解の進行が妨げられ,溶け残りが発生して目標組成に達しないことが起 […]
光学顕微鏡を用いて明瞭なFe-C系合金組織(フェライト,パーライト,セメンタイト,レイデブライト,マルテンサイト等)を観察するためには,どのような腐食液を用いるとよいのでしょうか?
Fe-C系合金の組織観察に用いられる代表的な腐食液として,「ナイタール」と「ピクラール」があります. ナイタールは,1.5mlの硝酸(比重d=1.42g/ml)を100mlのアルコール(メタノール,又はエタノール)に […]
鋳鋼, 鋳鉄について, 液相線温度よりどれくらい高い温度から鋳込むのが適当ですか.また, 鋳込み温度を液相線直上の温度から高くして行くと, 組織はどう変化していくのですか.
下にFe-Cの状態図を示します. 例えば, 共晶成分を狙う球状黒鉛鋳鉄の場合は, 大物では1153℃より100℃高い1250±30℃付近を狙います. 小物では, 湯流れ等の関係から液相線より250℃高い1400±30℃ […]
オーステナイトではFe原子間距離が広くなってC原子が移動することができますが,セルとセルとの結晶粒界を越えて移動することはできますか?
「セル境界でも結晶粒界でもC原子が移動できるか?」との事であれば,Yesです. 凝固後の温度低下で共析変態温度に達するまでにAGr線(Fe-C二元平衡複状態図のFe-G系)に沿ってγ中のC固溶度が低下し共析変態でγ⇒ […]
鉄系材料では,フェライト,オーステナイト,ベイナイト,マルテンサイトなどの組織の違いによって,どれくらいビッカース硬さやロックウェル硬さに違いがあるのでしょうか.
鋳鉄の基地組織は,フェライト,オーステナイト,パーライト,ベイナイト,マルテンサイトの順に硬くなります.材料の硬さは,それぞれの組織構成で異なりますが,フェライトのブリネル硬さは90~150HB程度,パーライトのブリネル […]
「魔法のフライパン」や「南部鉄器」などの良いといわれる調理器具の鉄の組織とはどういうものでしょうか.また,急須やフライパンなどはなぜ表面が黒いものが多いのでしょうか?
一般的な調理器具として使われる「南部鉄器」の組織として,白鋳鉄は避けなければなりません.その理由として,繰り返しの熱により,器具が割れたりするためにチル化した組織にならないように注意します.したがって,一般的な組織は片 […]
パーライト組織はフェライトとセメンタイトが層状となっていますが,組織中のフェライトとセメンタイトは初析のフェライト,セメンタイトと同じでしょうか?
ある炭素鋼がA3またはAcm変態点以上の温度かつ,組織は全てγ相(オーステナイト相)であり,ここから徐冷を行うとします.冷却が進み,亜共析鋼(0.77wtC%未満)の場合,A3変態点に達すると,フェライト相が過共析鋼( […]
球状黒鉛鋳鉄の製造において,球状化剤や接種剤の効果を活かすには,どのタイミングでどのような方法で加えるといいのですか?
健全な球状黒鉛鋳鉄品を製造するのに必須な溶湯処理技術の基本に関する良い質問ですが,製造条件により正解がいくつもあり回答者泣かせな質問でもあります. さて,結論から言えば,①処理剤の効果を活かすには,「処理剤に最適な処 […]
FCDの黒鉛球状化率算出について質問です.JIS G5502では100倍の顕微鏡画像5視野から球状化率を算出することになっていますが,視野の広さについて記載がありません.正しく算出するためには少なくともどれくらいの広さの視野について観察するべきでしょうか?
画像解析装置が普及し,黒鉛球状化率が「金属顕微鏡-CCD(CMOS)カメラ-画像解析ソフト」(画像解析装置)により算出される現状において,今回の質問はシンプルですが重要です. 現行のJIS G5502での黒鉛球状化率 […]
フェライト基地を腐食すると結晶粒界がはっきり見えますが,パーライト基地では粒界が見えづらいのはなぜですか? パーライトは、隣接するセルが融合しているのですか?
片状黒鉛鋳鉄の凝固過程では,共晶凝固が完了するとオーステナイトと黒鉛の混在組織となり,やがて共析変態温度に達するとオーステナイトはパーライトに変態し,常温では片状黒鉛とパーライト基地で構成された組織になります.初晶オー […]