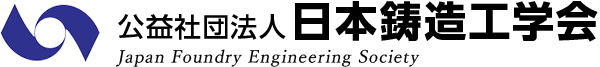鉄
成分分析装置もなく温度計もなかった古い時代に,鋳物師達はどうやって鋳鉄鋳物の溶湯性状を判断したのでしょうか.
昔の鋳鉄鋳物師達は,湯面模様によって溶湯性状を判断したと考えられます.キュポラ鋳鉄溶解では,溶湯性状が良くなるにつれて,湯面模様が笹の葉状から,麻の葉状,亀甲状へと変化していく事が知られています(図1の(a),(b),( […]
ヨーロッパでは30年前からワイヤー球状化処理が用いられていますが,日本では最近どうなっているのでしょうか?
日本でも近年,鋳鉄の球状化処理のためにワイヤー法が注目を集め,採用,または導入を検討する鋳物工場が増えています.それには下記の理由があると思います. 第一に『処理装置の発展』です.爆発的な球状化処理反応にも耐えうる装置が […]
CV鋳鉄はFC(片状黒鉛鋳鉄)とFCD(球状黒鉛鋳鉄)の両方の特性を持っていますが,あまり普及されていません.どうしてでしょうか?
FCVは,コンパクティッド・バーミキュラ鋳鉄(芋虫鋳鉄)と呼ばれ,高強度のFCD(ダクタイル鋳鉄)と被切削性に優れたFC(片状黒鉛鋳鉄)のイイトコ取りとして注目され,現在量産品では油圧バルブ,ディーゼルエンジンブロック […]
鋳鉄の溶湯の中から非金属の黒鉛が出現するのはどうしてですか.さらにオーステナイトからも黒鉛が現れるのはなぜですか? 教えてください
確かに不思議な現象ですね.謎解きは,昔習った理科の「溶液の勉強」で溶媒と溶質,飽和溶液と過飽和溶液,溶解と沈殿,溶解度などを思い出そう. 鋳鉄の溶湯とは,溶媒が液体の鉄で,溶質が主に炭素(C)とけい素(Si)の溶液と考 […]
鋳鉄を勉強すると出てくる鉄-炭素二元平衡状態図は、どんな時にどのように役立つのか?
状態図と熱力学のエリンガム図及び元素周期律表は、鋳造における3種の神器とも言われているものである.状態図はある化学組成と温度でどのような状態(相または組織)になるかを教えてくれる. Fe-C状態図(下図)は,他の合金の状 […]
「炭素当量」の出自は?同じCE値でもC%が高い時とSi%が高い時の溶湯の特性を共晶凝固と共析変態過程及びひけ傾向について教えてください.
炭素当量(Carbon Equivalent:CE )とは鋳鉄中のSi,P量の影響の度合を⊿関数1)で示すC %として表し,これと実際の鋳鉄中のC%との和の値で,次の(1)式で表すことが多くあります. CE=C%+(Si […]
Fe-C系状態図中の言葉の意味を教えてください.平衡状態図,初晶,共晶,共析,液相線,固相線,A1変態点,A3線,Acm線などイメージがわきません.
一般に平衡状態図とは,横軸に組成(含有量),縦軸に温度を取り,ある組成の溶液や合金などが,ある温度でどのような状態で存在している示す地図と考えると解りやすいでしょう. そこでFe-C系複平衡状態図は,実線のFe-Fe3C […]
鋳鉄溶解炉としてキュポラが誘導炉に変わってきていますが,その理由は?
キュポラが誘導炉に変わってきた理由は企業の操業環境によって違うと思いますが,その代表的なものを紹介したいと思います. 一つ目は,キュポラはコークスを燃焼させ連続的に溶解,溶湯を作る設備であることです.連続操業の場合に […]
片状黒鉛の形状はA型が良い,と言われる理由は?
片状黒鉛鋳鉄の機械的性質は黒鉛形状と基地組織に大きく影響されており,「A型黒鉛が良い」と言われています.昔は,A型の方が黒鉛の先端が丸いので,応力集中が少なくなるため機械的性質が良くなるといわれた時期もありました.しか […]
FCD材の疲労試験において,回転曲げと平面曲げの疲労限度はほぼ同じ値でしょうか?もし,異なるのであればどちらの値が高く示し,それはなぜでしょうか?
回転曲げ疲労試験とは,一定の曲げモーメントを作用させた丸棒を回転させ,試験片平行部の表面に繰返し,曲げ応力を負荷させる疲労試験です.また,平面曲げ疲労試験とは,平板試験片に繰返し曲げ応力を負荷する疲労試験のことです.どち […]