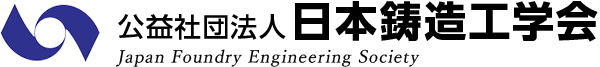シェルモールドやコールドボックスの砂の充填シミュレーションにはどんな手順,手法が用いられますか?
シェルモールドやコールドボックスの砂の充填ではブロー造型が多く使用されます.ブロー造型の場合,鋳枠あるいはコアボックスへ砂を運ぶ工程と,砂の配列が変化して粗から密になる砂の圧密化工程とに分けて考えると良いでしょう. まず […]
自硬性の砂評価はLOIが主流で,酸消費量やソーダ分等はあまり現場では使用されておりません.どのプロセスでもLOIで評価していればいいのでしょうか? 各プロセスでLOI以外の評価をした方が良い評価項目はありますか? また,プロセスによってはLOIよりもいい評価項目はあるのでしょうか?
LOI(Loss on Ignition,強熱減量)は1000℃の減量%で,有機自硬性の評価に主に用い,回収砂では残留樹脂相当です.回収砂の再生状態やガス欠陥予測ができます.加えて,粒度分布や通気度を評価すると予測精度が […]
銅合金溶湯の脱酸にCu-P合金が使われますが,なぜ脱酸が出来るのでしょうか?
銅合金の溶解は,通常弱酸化性雰囲気で行われるので,溶湯中に溶け込んだ酸素[O]が存在します.この状態で凝固が進行すると水素と結びついて鋳塊中に水蒸気ガス気泡を形成する場合や,易酸化性金属元素と結合してその金属酸化物となっ […]
ねずみ鋳鉄の鋳物内で,A型黒鉛にD型黒鉛が混在していますが,なぜですか?
図1に,A型黒鉛にD型黒鉛が混在する組織写真の一例を示します.このような組織になる要因として,以下のことが考えられます. 接種が効かなかった可能性があります.接種剤がうまく溶けなければ,黒鉛の核が少なくなってすぐフェーデ […]
純銅系の鋳物では,黄銅や青銅に比べガス気泡欠陥ができやすいのは何故ですか.
銅合金鋳物に発生するガス気泡には,水蒸気ガス気泡と水素ガス気泡の2種類があります.どちらが発生するかは,溶銅に溶け込んだ酸素量と水素量のバランスによって決まり,同じ水蒸気分圧下では酸素量と水素量は逆相関の関係にあります […]
日本,中国,インドなどの生砂の違いは何でしょうか?
生砂に求められる条件は,適切な化学組成及び物理的性質を有し,かつ砂粒は適度な粒度分布を有し,粒形は丸形に近いものです. 日本で使用されている生砂は,国産が半分弱でその他はオーストラリアやベトナムからの輸入です.国産砂の […]
Zn-Al合金で室温まで冷えた鋳物が後になって熱くなっていることがあります.どうしてそんなことが起こるのでしょうか?
「鋳物」を大きな意味での鋳造品と考えると表面温度上昇の原因として次のことが考えられます. 熱が溜まりやすい部分がある鋳物,例えば,厚肉部分がある,中子がある,大きな湯口や押し湯が付けられている場合には,表面が冷えても内部 […]
ねずみ鋳鉄FC300にはSnを添加し,球状黒鉛鋳鉄FCD700にはCuを添加して製造しています.それぞれ高強度にするために,パーライト量を増やす目的なのでしょうか.逆に,ねずみ鋳鉄にCuを,球状黒鉛鋳鉄にSnをそれぞれ添加しても問題ないのでしょうか?
高強度にするためにねずみ鋳鉄または球状黒鉛鋳鉄にSnまたはCuをそれぞれ適量添加し,ほぼオールパーライトにすることが目的です. 逆にねずみ鋳鉄にCuを,球状黒鉛鋳鉄にSnを添加しても問題ありません. 生産上高強度FCに […]
接種する事で組織が微細化され強靭になると言われるのはなぜでしょうか? 共晶セルを微細化すると結晶粒界の面積が増加するので,微細化しない方が引張強さは強いのではないでしょうか?
強靭化の度合にもよりますが,接種の効果も強靭化の一因子です.とは言え高強度で高延性を得られるかといえば,黒鉛化促進接種剤では延性向上を期待できますが,強度は低下し,パーライト促進接種剤を使えば逆となります.ご存知のように […]
黄銅は金型鋳造ができるのに青銅では難しいのはなぜですか.
生産性の向上,作業環境の改善といった観点から青銅の金型鋳造は昔から望まれてきましたが,多くの問題があり,実用化は進んでいません. 青銅系の合金は黄銅系の合金と比較して凝固温度範囲が広く,粥状凝固する合金です.凝固温度範囲 […]