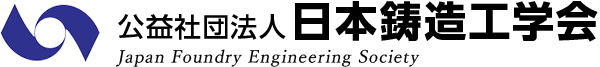鉄
鋳鉄の溶湯は,金属なのに固まると非金属の黒鉛が出てきます.どうしてなのか教えてください.
鋳鉄は,鉄(Fe)と炭素(C)の合金であることはご了解のことと思います.このような合金は,溶媒(鋳鉄の場合は鉄)中に溶質(この場合炭素)が溶け込んでいると,溶媒の凝固温度が低下することがあります.さらに鉄の原子の結合(金 […]
ダクタイルはFCにくらべて,なぜ,ひけやすいのでしょうか
鋳鋼やアルミニウムなどは,凝固収縮を補うために大きな押湯を必要とします.しかし,鋳鉄では黒鉛晶出による体積の増加があるので,基地(鉄)が凝固時に収縮しても,それを上回る程度の膨張があって,そのためにひけがない,あるいは発 […]
亜共晶組成の方がチル化しやすいのですか?
まず,鋳鉄の溶湯は,塩水(水と塩)や砂糖水(水と砂糖)と同じような溶液である.鋳鉄の場合は高温の鉄(液体)と含有成分(C,Si,Mnなど)になる.ここでは炭素が液体の鉄の中に溶け込んでいる1500℃の溶液が凝固するまで […]
凝固条件や熱処理条件がわからない場合,マルテンサイトとソルバイトの組織の違いを見分けるのに,どのような点に注意を払えばいいのですか.
前号に続き,組織の違いについての質問である。マルテンサイトとソルバイトについても,金属顕微鏡を用いて400~700倍程度の倍率で観察するとよい。実際に,共析組成(0.8%C)の鋼材((株)山本科学工具研究社製)を用いて, […]
凝固条件や熱処理条件がわからない場合,上部ベイナイトと下部ベイナイトの組織の違いを見分けるのに,どのような点に注意を払えばいいのですか.
鉄鋼に関する書物を読んでいると,層状(ラメラ状),羽毛状,針状,笹の葉状,ラス状,レンズ状といった言葉が飛び交う.しかし,初学者にしてみれば,本文中に掲載されているイラストや組織写真を見ても,どの部分について説明されてい […]
光学顕微鏡で炭素鋼を観察すると黒と白の模様が現れます.どうしてフェライトは白く,パーライトは黒い縞なのでしょうか.
組織観察を行うためには,一般に落射照明による明視野の光学顕微鏡(金属顕微鏡)を用います.試料を鏡面研磨した状態で光学顕微鏡で観察しても金属組織は現れません.試料表面に当たる光が均一に反射されるためです.そこで組織を見る […]
接種をすれば引張強さが向上する事は事実です.しかし,接種をすれば黒鉛化が促進されて黒鉛量が増加し,密度は下がるはずですが,なぜ接種をして黒鉛化を促進した方が強度が向上するのでしょうか.
接種は,鋳込み直前の鋳鉄溶湯にフェロシリコン(Fe-Si)やカルシウムシリコン(Ca-Si)などを少量添加して凝固組織を改善し,機械的性質の向上を図る溶湯処理法の1つです.接種を施すことにより,鋳鉄の組織が改善され,チル […]
オーステンパ処理を施すとベイナイト組織が現れます.等温変態処理温度の違いにより上部(羽毛状組織)と下部(針状組織)のベイナイトに分かれますが,なぜ組織に違いがみられるのでしょうか.上部と下部のベイナイトで機械的性質(引張強さや硬さ)はどの程度異なるのでしょうか.
鋳造品におけるオーステンパ処理の代表として,オーステンパ球状黒鉛鋳鉄(ADI:Austempered Ductile Iron)を念頭にお答えしたいと思います. 「羽毛状」「針状」とは主に光学顕微鏡による組織写真のイメー […]
ねずみ鋳鉄の鋳物内で,A型黒鉛にD型黒鉛が混在していますが,なぜですか?
図1に,A型黒鉛にD型黒鉛が混在する組織写真の一例を示します.このような組織になる要因として,以下のことが考えられます. 接種が効かなかった可能性があります.接種剤がうまく溶けなければ,黒鉛の核が少なくなってすぐフェーデ […]
ねずみ鋳鉄FC300にはSnを添加し,球状黒鉛鋳鉄FCD700にはCuを添加して製造しています.それぞれ高強度にするために,パーライト量を増やす目的なのでしょうか.逆に,ねずみ鋳鉄にCuを,球状黒鉛鋳鉄にSnをそれぞれ添加しても問題ないのでしょうか?
高強度にするためにねずみ鋳鉄または球状黒鉛鋳鉄にSnまたはCuをそれぞれ適量添加し,ほぼオールパーライトにすることが目的です. 逆にねずみ鋳鉄にCuを,球状黒鉛鋳鉄にSnを添加しても問題ありません. 生産上高強度FCに […]