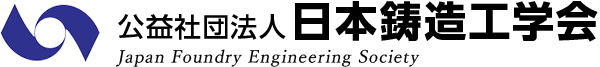アルミ合金鋳物を熱処理するとなぜ硬くなるの?
凝固点直下の高温で合金を保持すると,Alの結晶構造の中にCu,Mg,Si等のような他の合金元素の原子が均一に溶け込んだ“固溶体”状態になっています.このような状態にすることを“溶体化処理”と呼びます.この状態からゆっく […]
チャンキー黒鉛は,凝固時間が長い厚肉鋳物の最終凝固部に生成されることが一般的に知られている.更に溶湯処理剤(球状化剤や接種剤)を構成するCa,Si,Ce,Niなどの元素がチャンキー黒鉛の生成に影響を与えると報告されている. 一方,数kg~十数kgの小物鋳造現場での経験では、チャンキー黒鉛が出やすい製品において,注湯温度が高いより低い時の方が発生しやすい.これは,厚肉大物球状黒鉛品と真逆になると思われますが何故でしょうか?
注湯温度の影響に関しては,一般的に高温注湯の方がチャンキー黒鉛出やすいことが知られています1).厚肉大物品に於いて低い注湯温度の方が出やすいとの知見は殆どありません.だからと言って,貴殿の質問を否定することも出来ません. […]
現場的にBa-Ca-Si系二次(注湯流用)接種剤を多めに使用すると,チャンキー黒鉛が生じやすくなるのは何故でしょうか? また,同一鋳物部位においてチャンキー黒鉛が出やすくなるとその部位には引けが小さくなる傾向があるが,それはなぜでしょうか?
ご質問の内容には,鋳物のサイズ,化学組成など具体性が無いので一概に言えませんが,チャンキー黒鉛と言ってよいかどうか分かりません.Ba-Ca-Si系接種剤は、その化学組成からするとFe70Siに比べて溶湯に融け込みづらいも […]
減圧凝固試料の見方は?
溶湯の品質は 化学成分,ガス,介在物,温度で評価されます.減圧凝固法は,溶湯中に含まれる水素ガス量を目視で調べる方法で,目視的な評価として,簡易的に判定可能なため,製造現場において多く用いられます. 方法は,図1に示 […]
アルミダイカストの溶湯保持温度を極力低くしたいのですが,何度ぐらいまで低くすることができますか
ダイカストの溶湯温度は通常660℃~680℃の範囲で設定されています.溶湯温度を低くすると第1にスリーブ中で凝固が進み,湯回り不良や湯境などの充填不良が発生します.また第2に保持炉の中でスラッジが生成し,ハードスポット […]
鋳鉄を鋳肌のまま使用する場合と表面仕上げを施した場合では,強度にどれほどの差がありますか?
鋳鉄の鋳肌には砂との焼付きによる黒皮酸化層や表面での欠陥(巣や介在物,あるいは異常組織)などが存在します.さらに鋳肌の表面粗さは不均一であり,その凹凸が著しい場合には応力集中による影響を考える必要もあります.引張強さはそ […]
残留Mgが低いFCD溶湯を丸棒試験片(例えば、直径φ15,30mm)に鋳込んだとき、球状化率が高い部分と低い部分が図1のように何層ものリング状に分布するのは何故でしょうか?
図1 丸棒試験片にリング状に破面の色が何層も見える現象は,その丸棒試験片を得る条件が関係し,例えば注湯温度や解枠後の冷却条件(基地組織への影響)がばらつくことも一因です.FCDのパーライトとフェライトが […]
Kモールド試験法とは何ですか?
溶湯の品質は 化学成分,ガス,介在物,温度で評価されます.Kモールド法は,溶湯中に含まれる介在物を調べる目的で,破断面観察法として一般に使用される方法です.図1に示すようなアルミニウム製の鋳型に溶湯を鋳込み,凝固させた後 […]
回転曲げ疲労試験により得たS-N曲線において,FCD700材で鋳放し材よりも熱処理材の方が傾きが立っているのは何故でしょうか
FCD700材を熱処理すると引張強さ,硬さが向上する様に静的機械的性質が上昇します.しかし,伸びや絞りといった延性特性は低下します.これはFCD700材の鋳放し材がフェライト組織とパーライト組織の二相組織であるのに対し […]
軽量化のためにマグネシウムダイカストを使用したいと思っています。エンジンのそばの部品のカバーですが、どのようなことに注意して設計すれば良いでしょうか?
マグネシウム合金は実用金属の中で最も軽量な金属であり,鉄鋼材料やアルミニウム合金からの置き換えで,軽量化を図ることができます.しかし,機械的性質などの材料特性が異なるため,注意する必要があります.カバー類であれば,一般 […]