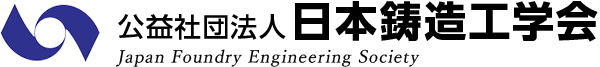鉄
接種する事で組織が微細化され強靭になると言われるのはなぜでしょうか? 共晶セルを微細化すると結晶粒界の面積が増加するので,微細化しない方が引張強さは強いのではないでしょうか?
強靭化の度合にもよりますが,接種の効果も強靭化の一因子です.とは言え高強度で高延性を得られるかといえば,黒鉛化促進接種剤では延性向上を期待できますが,強度は低下し,パーライト促進接種剤を使えば逆となります.ご存知のように […]
Fe-C系状態図で黒鉛の晶出量を求めると数%ですが,顕微鏡組織から判定すると10~15%に見え,文献にもそう書かれています.この違いはなんですか?
Fe-C系状態図における黒鉛晶出量は,重量%で表示されています.一方,顕微鏡組織における黒鉛晶出量は体積%もしくは面積%で表示されています.よって,状態図の重量と顕微鏡組織での黒鉛体積%の間には,近似式で計算すると,式( […]
鋳鉄材料の規格は引張強さや伸びで規定されていますが, 値を求めるときの有効数字はどこまでですか? 具体的に教えてください.
引張試験は特殊な場合(規程の試験片が採取できないなど)を除いて,基本的にはJIS Z 2241「金属材料引張試験方法」に則った方法で実施する必要があります.一般に引張試験結果は, 材料規格に規定のない場合は, 少なくとも […]
接種は本当に黒鉛化を促進するのでしょうか?
Fe-G系凝固(共晶Fe3C:チルが無い)した鋳鉄の黒鉛量は,おおよそ凝固時の晶出量(Fe-C二元複平衡状態図のE´点)とその後の共析変態完了時までの析出量の和になります.接種は,基地組織(フェライト/パーライト率)にも […]
鋳鉄溶湯の熱分析で得られる冷却微分曲線で,凝固終了時の傾きがマイナスからプラスに転じる点の角度θが小さいほど引けにくい溶湯だという文献がありますが,この理屈が良く分かりません.どういった理由で角度θが小さいと引けにくい溶湯だと言えるのでしょうか?
θが小さいことは熱電対を挿入した部位の熱伝導率が小さいことを意味しており,熱伝導率が小さくなる原因は,ひけ巣(空洞)の存在と考えられています.なぜ冷却速度曲線(冷却微分曲線)にθが表れるのかという点からもう少し詳しく説明 […]
「圧力容器(FC300)穴加工後の水圧検査で鋳肌面に微小な漏れが発生しました.原因としまして,どのようなことなどが考えられるでしょうか.また、黒鉛や粒界を介して圧漏れすることはあるのでしょうか.
漏れるということは内側と外側がつながった不良ということなので,考えられるのは割れや湯境、表面から見えにくい異物かみ(砂、ノロ)等の不良が考えられます.これらの不良は目視でよく見れば分かると思いますが,微小なものはわかりに […]
ねずみ鋳鉄FC200(JISG5501)で,別鋳込み供試材の規格がφ30に制定されているのは機械試験に使用するためでしょうか? 8B試験片にてφ20で鋳造し,φ12.5で引張試験を行うのは間違っていますか?
鋳鉄の引張強さは黒鉛量,炭素飽和度(Sc),肉厚などによって変化します.試験片の直径が小さい場合は,その鋳物の冷却速度が大きなり,引張強さは増大します.そこでJISなどでは,片状黒鉛鋳鉄の標準強さは直径30mmの試験の値 […]
鉄材の湯流れ性がCE値の違いで変化することを現場で経験しました.なぜでしょうか? また,湯流れ性は一般にどのように測定して判断するのでしょうか.
湯流れ性(流動性)は,鋳込温度が高くなれば凝固時間(流動寿命)が長くなり,その間に流れる距離も長くなります.過熱温度(=鋳込温度-液相温度)と流動性との間にほぼ直線関係が成り立つことが,実験的に確かめられています.鋳鉄の […]
球状黒鉛鋳鉄の黒鉛粒数や球状化率を測定する際に,15μm以下の小さい黒鉛は無視することになっています(JIS).15μmに決めた根拠は?
球状黒鉛鋳鉄について日本独自の黒鉛形状分類法と黒鉛球状化率の判定方法を定めた 記録が「鋳物40巻(1968)P296」に紹介されています.当時の日本鋳物協会特殊鋳鉄部会の10数回の委員会による審議の結果作成されたものです […]
FC(ねずみ鋳鉄)に,お酢などを使用して意図的に錆びさせてその錆を磨き,野菜クズなどを炒めて熱し,油を塗る(熱する・油を塗る工程は何度か行う)と,一度錆びさせたことで油の染込みが良くなって錆びにくくなるという効果は期待できるでしょうか?
「錆びにくくなるという効果」とありますので,最初に南部鉄瓶の防錆法について簡単に説明します.南部鉄瓶のお湯が入る内面の防錆は酸化皮膜で,模様のある外面は漆(うるし)の皮膜で防錆しています.内面の酸化皮膜(黒錆,Fe3O4 […]